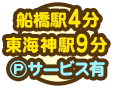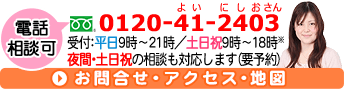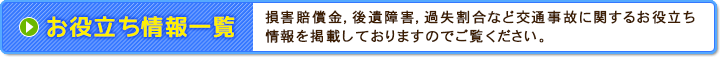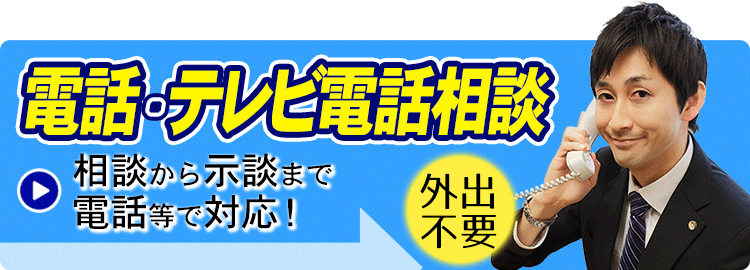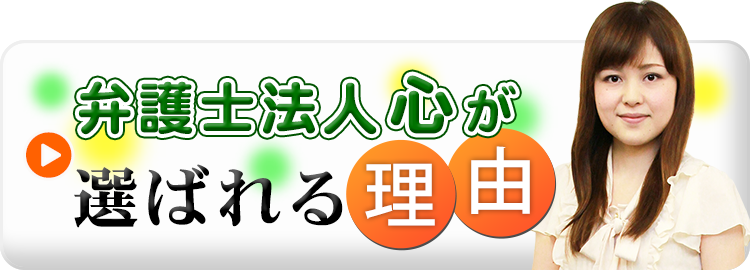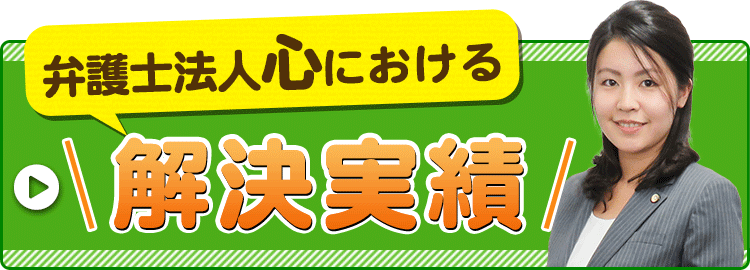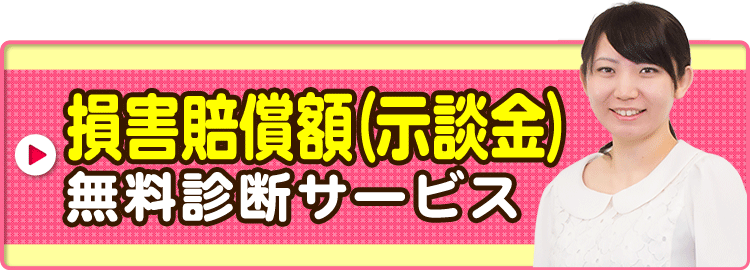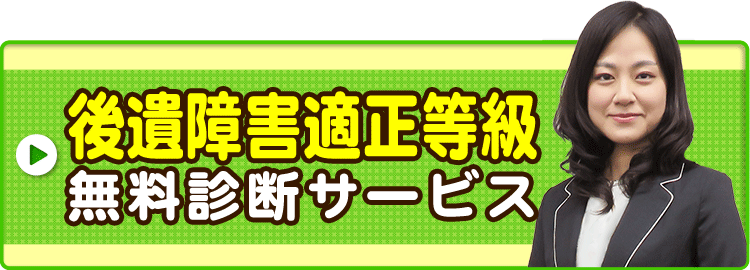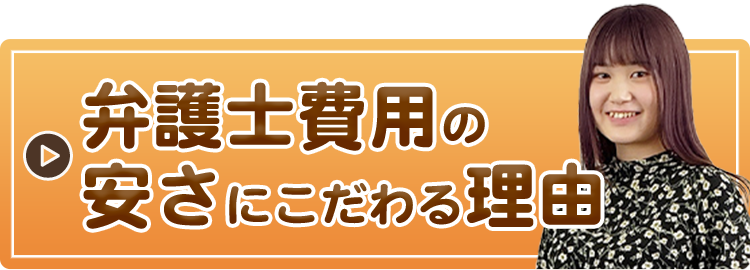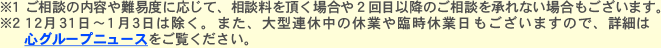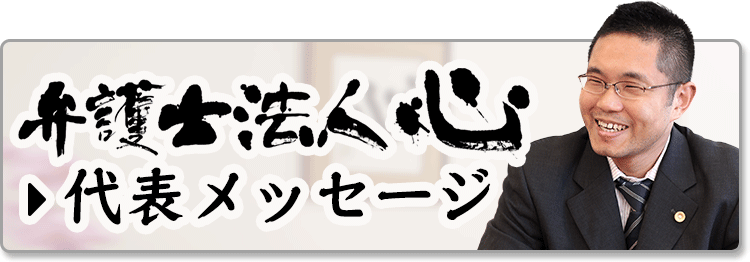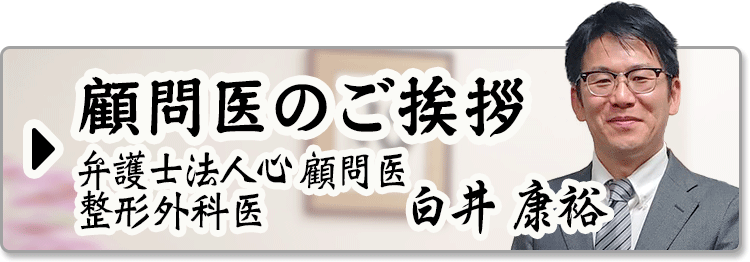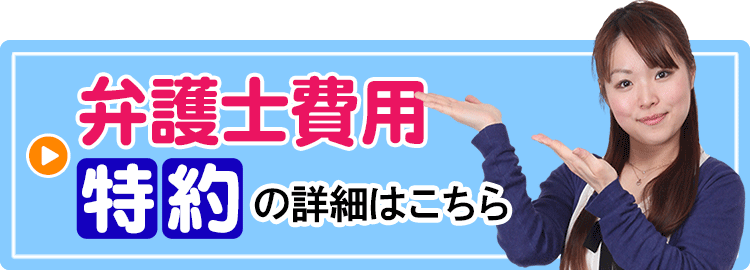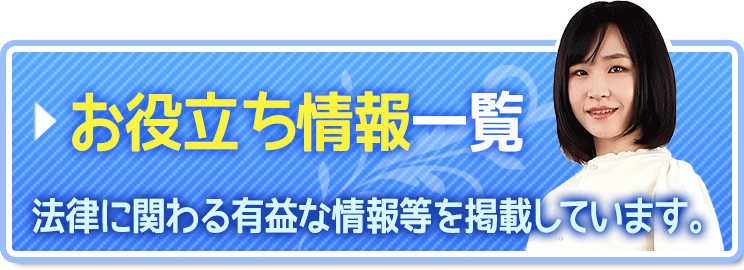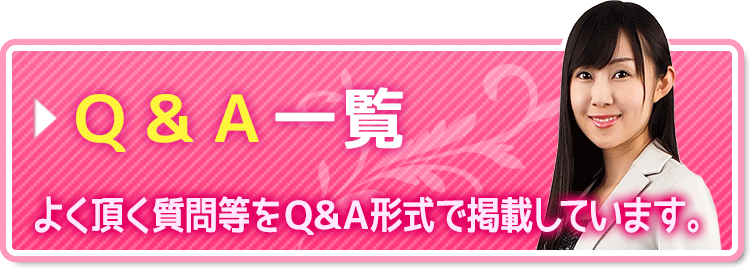高次脳機能障害が症状固定とされる状態と時期について教えてください。
1 高次脳機能障害と症状固定
脳の損傷(脳挫傷、脳内出血など)により損なわれた脳の機能は、リハビリにより回復することがありますが、リハビリを続けても症状の改善が認められなくなった時点が、症状固定とされる状態となります。
また、高次脳機能障害の場合、原因となる脳の損傷発生から症状固定まで、1年以上かかることが多いとされています。
高次脳機能障害は、脳挫傷、脳内出血などにより、脳が損傷することが原因で発生します。
脳は、記憶を司る箇所、言語を司る箇所といったように、箇所によって司るべき機能が異なります。
このため、例えば、言語を司る箇所に脳の損傷が発生した場合、言語機能の障害(言葉を発することができなくなる、など。)が生じることになります。
しかし、障害が発生しても、リハビリをすることで、改善することも知られています。
2 症状固定について
症状固定とは、事故後の症状が、治療やリハビリにより一定程度改善したものの、治癒までには至らない状態であり、かつ、その後の症状の改善が見込まれない状態を言います。
高次脳機能障害の場合、言語や記憶といった機能の障害が生じた後、これが改善しつつも、完全な回復には至らず、かつ、その後の改善が見込まれないとされたときには、症状固定の状態に至ったことになります。
3 高次脳機能障害に対するリハビリについて
高次脳機能障害に対するリハビリについては、専門的な知識や技術が必要となるため、通常の医療機関ではなく、高次脳機能障害に対するリハビリを専門に行う施設で行われることとが多いです。
リハビリによる回復の程度は、被害者の症例により異なりますが、1年程度の長期のリハビリが必要とされることが多いようです。
障害の程度が小さかったり、被害者が若年である場合は、回復の程度が大きいことがあります。
また、損傷した機能の回復のための医学的な支援だけではなく、自立した生活が送れるようにしたり、就労支援を目的とした対応も行われています。
一例として、国立障害者リハビリセンターの高次脳機能障害情報支援センターのホームページでは、リバビリ期間が長期に及ぶこと、その間、様々な職種の職員がチームとなって対応することにつき、記載されています。
4 症状固定とされた後の対応について
症状固定は、先にお伝えしたとおり、治癒までには至らない状態をいい、何らかの障害が残った状態となります。
このため、個々の症状に基づき、後遺障害の認定を受けることについての検討と、後遺障害としての認定を求めるための申請が必要となります。
非器質性精神障害と後遺障害申請に関するQ&A 交通事故により、むちうち(頸椎捻挫、腰椎捻挫)と診断され、治療を継続中ですが、弁護士に相談した方がよいですか?